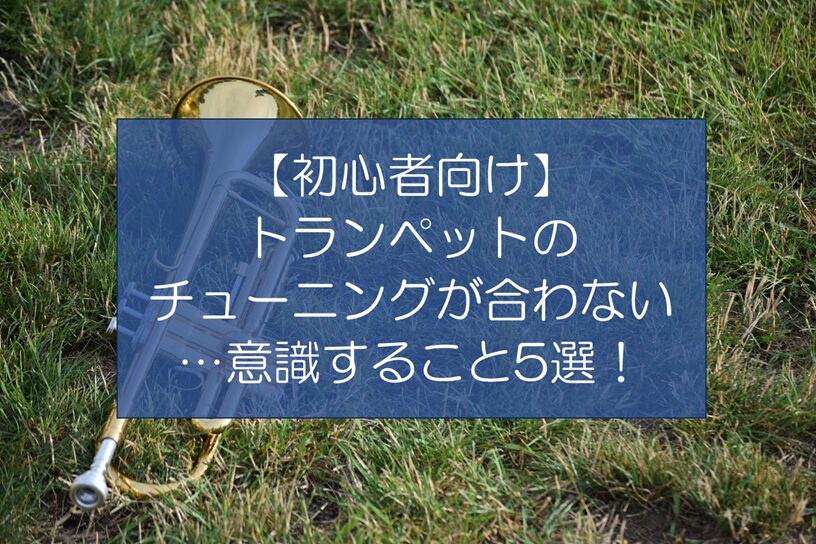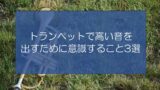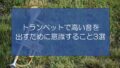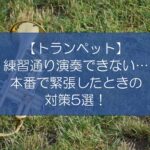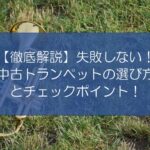トランペットを吹いていて、「なんだかピッチが合っていない気がする…」「合奏で自分の音が浮いてしまう…」と感じたことはありませんか?
チューナーで合わせたつもりなのに、実際に演奏すると音がズレてしまうことはよくあります。実は、チューニングをしっかり合わせるためには、単にチューナーを見て調整するだけでは不十分 なのです。
そこで本記事では、チューニングを合わせるために意識すべき3つのポイント を解説します!
1. 頭の中に正しい基準となる音を持つ
チューニングを合わせるためには、まず「正しい音程とはどんな音なのか?」を自分の耳で理解しておく必要があります。
頭の中に正しい音程がないと、合奏の最初にチューニングを合わせたとしても、すぐに音がずれてしまいます。
まずは普段からピアノやチューナーの音を聴いて、B♭の音や他の音を頭に覚え込みましょう。
まずは「耳を使って音を合わせる」ことを意識し、チューナーに頼りすぎないようにしましょう!
2. トランペットを正しく鳴らすことができる
一旦音程を合わせたとしても、吹き方が安定していないと音程はズレてしまいます。
トランペットは同じ「ド」の音でも、吹き方で「高めのド」や「低めのド」を出すことができてしまいます。
まずは楽器のツボを捉えて、トランペットを無理なく演奏できるようにしましょう。
トランペットのツボについては、下記リンクも参考にしてください。
3. 楽器の調整を適切に行う
チューニングを行う
トランペットの主管抜差管(チューニングスライド) を適切に調整することで、正しい基準の音程に近づけることができます。一般的に「チューニング」とは、この調整作業を指します。
🔹 チューニングの基本手順
- チューナーを使い、B♭を吹く
- 音程が高い場合 → チューニングスライドを少し引く
- 音程が低い場合 → チューニングスライドを少し押し込む
ちなみにトランペットのチューニングスライドは、基本的に少し抜いておくと正しい音程になるように設計されているそうです。このことを念頭にチューニングを行いましょう。
また、気温や演奏状況によって音程は変化するため、以下の点にも注意が必要です。
- 気温が高いと音程が上がり、低いと下がる
- 長時間吹いていると、楽器が温まり、音程が上がる
このため、本番前だけでなく、演奏中も音程の変化を意識しながら調整 することが大切です。
楽器の構造を理解する
トランペットは楽器の構造上、特定の音が基準より高くなったり低くなったりする 特性があります。
音程が合わない原因が、単純に楽器の構造上の問題ということもあるので、以下の内容を押さえておきましょう。
倍音の影響を受ける
トランペットは 倍音列 に基づいて音を出す楽器です。そのため、純正律という音律の影響を受け、代表的な例として、ピストンを押さないで吹く場合にの音程に、以下のような傾向が見られます。
- 高くなりやすい音 → チューニングB♭の下のソ(G)
- 低くなりやすい音 → チューニングB♭のミ(E)
細かい内容は割愛しますが、他の音も高くなったり低くなります。よく使う音を中心に音の高低の傾向を把握しておきましょう。
ピストンの組み合わせによる音程の変化
トランペットでは、2つ以上のピストンを押したときに音程が高くなりやすい 傾向があります。
- 1,2,3番ピストンの「A(ラ)」は、3番ピストンの「A」より高くなりやすい
- 1,3番ピストンの「D(レ)」は高くなりやすいく、1,2,3番「C#(ド#)」は、さらに高くなりやすい
これを補正するために、1番・3番抜差管(ピストン抜差管)を調整することが重要 です。
曲によって、楽器の調整を適切に行うことで、無理にアンブシュアや息で音程を合わせようとせず、自然な演奏ができるようになります。
4. まとめ
チューニングを合わせるために意識することを解説しました。
チューニングは、ただチューナーを見てスライドを動かすだけでは完璧に合いません。正しい基準音を持ち、正しい吹き方をし、楽器の調整を適切に行うこと が大切です。
ぜひこれらのポイントを意識して、正確な音程で演奏できるように練習してみてください!